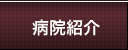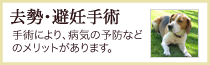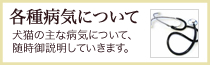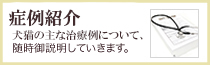膵臓の急性炎症です。どの犬でも突然発症する可能性があります。
脂肪の過剰摂取などが一因として挙げられますが、原因を特定できない場合のほうが多いです。
「元気消失」「食欲廃絶」「嘔吐」「下痢」「腹痛」などの症状がみられます。突然ものすごく体調が悪くなります。
「症状」「血液検査」「超音波検査」などから総合的に診断します。
・血液検査
赤血球、白血球、血小板、腎臓、肝臓、電解質、CRP、リパーゼなどの項目を測定します。
・超音波検査
腹部全体を詳細に検査します。
輸液、鎮痛剤、制吐剤、抗炎症薬などによって治療を行います。
適切に治療すれば完治する場合が多いです。治療が遅れたり、他の病気を併発していたりすると亡くなる可能性もあります。
以下は細かな話となります。
膵炎は症状だけで一目でわかる病気ではありません。同様の症状がみられる病気として「急性胃腸炎」「急性肝炎」「胆管閉塞」「異物による腸閉塞」「急性出血性下痢症候群」「中毒」「前立腺炎」「腎盂腎炎」「子宮蓄膿症」「アジソン病」なども考えられますので、そのような病気がないかどうかも含めて検査で確認する必要があります。血液検査と超音波検査は必須であり、必要に応じてX線検査、尿検査、糞便検査なども行ったほうがよいでしょう。
膵炎の検査としては「リパーゼ(血液検査)」「超音波検査」が最重要となりますが、どちらも100%の信頼性はありません。繰り返しになりますが、総合的な判断が必要となります。
リパーゼは膵臓から分泌される消化酵素であり、膵炎になると血液中のリパーゼ濃度が上昇します。「cPLI(IDEXX)」と「v-LIP(富士フイルム)」という2つの検査があり、cPLIのほうが知名度がありますがv-LIPでもほぼ同様の信頼性が報告されています。どちらでもよいのですが、当院では院内で簡単に測れて価格も安いv-LIPを測定しております。
超音波検査による膵臓の描出はやや難しいです。機械の性能と獣医師の技術が必要であり、犬の種類や性格によってはさらに難しくなる場合もあります(柴犬など)。
診断において注意しなければいけないのは、「リパーゼが高くても膵炎(だけ)とは限らない」という点です。具体的には「異物による腸閉塞」「子宮蓄膿症」などでもリパーゼが高値になる場合がありますので、リパーゼが高いだけで膵炎と診断すると大変なことになる可能性があります。他の病気が存在しないかどうかを入念に調べる必要があり、特に超音波検査で膵臓以外の臓器も確認することが重要となります。
軽症例または発症し始めの段階では、一過性の胃腸炎なのか、急性膵炎のような重篤な病気なのか、症状からは判断が難しい場合もあります。一過性の胃腸炎であれば整腸剤や制吐薬などによる対症療法でよいのですが、急性膵炎では集中的な治療が必要となります。目安としては、下痢や嘔吐だけでなく元気や食欲の低下もみられる場合には対症療法ではなく各種検査を行ったほうがよいでしょう。また、1〜2日対症療法を行っても改善しないような場合にも検査を行ったほうがよいでしょう。
一般的には「異物による腸閉塞」「急性胃腸炎」が主な鑑別疾患となります。急に吐くようになって状態も悪い場合は、異物がないかどうかは必ず確認しなければいけません。血液検査や超音波検査で異常が認められず、異物や他の疾患の可能性も低そうであれば、胃腸炎と仮診断して治療を開始することになるかと思います。膵炎と胃腸炎は治療法が大きくは変わりませんので、最初から診断がつかなくても大した問題にはなりません。しかし、異物や子宮蓄膿症では治療法が大きく変わってきますから本当に注意が必要です。
重度の急性膵炎は、治療を行っても1日や2日では治りません。ぐったりした状態がしばらく続きますので不安になる方もいらっしゃると思いますが、あきらめずに治療を続けることにより完治させることが可能となります。
治療としては輸液が最重要です。飲み薬だけでは治療できません。重症であれば入院させて静脈輸液を行い、軽症であれば毎日通院してもらい皮下輸液を行います。
急性膵炎では激しい痛みが生じますので、鎮痛薬は必ず使用します。一般的な解熱鎮痛薬(NSAIDS)ではなく、「ブプレノルフィン」「トラマドール」「フェンタニル」などのオピオイド系の鎮痛薬を使用することが多いです。
吐いていれば制吐薬、下痢をしていれば整腸剤や止瀉薬などの投薬も行います。
その他の治療法として、抗炎症薬(ステロイド、フザプラジブ)を使用する場合もあります。
膵炎の治療において「ステロイド」または「フザプラジブ(商品名はブレンダまたはブレンダZ、以下ブレンダZと記載)」を使用する場合があります。
ステロイドは犬の急性膵炎への有効性が報告されています。ただし、副作用や他の併発疾患への影響も考えながら使用しなければいけません。
ブレンダZは膵炎の治療薬として認可を取っている薬です。特効薬みたいなイメージが一部であるようですが、そこまで完璧に効くわけではありません。治療のメインは輸液であり、あくまで補助的な位置付けとなります。かなり高額な薬ですから、軽症例でも当たり前のように勧めるのはどうだろうかと個人的には思っております。ブレンダZを強く勧めない病院は費用負担を考えていると思って間違いありませんので、勉強不足などと誤解されないようにお願いいたします。
現状ではステロイドとブレンダZを比較した研究はありませんので、どちらが優れているのかは不明です。個人的には同等に効くという認識でおりますので、コストパフォーマンスを考えるとステロイドでよいのではないかと思っております。
なお、ステロイドにしてもブレンダZにしても、膵炎治療で必ず使わなければいけないわけではありません。個人的には重症例において使用するようにしております。ステロイドを選択することが多いですが、ステロイドを使いたくない時(心臓病がある場合など)にはブレンダZを使うこともあります。あとは飼い主さんの意向しだいです。
膵炎に起因して胆管閉塞が生じる場合があります。黄疸の症状が出ていたら胆管閉塞が生じている可能性が高いです。
治療としては、膵炎の治療を集中的に行うということで変わりはありません。膵炎が改善してくれば胆管閉塞も治まります。手術が選択されることはほぼありません。
膵炎治療時の絶食は不要です。絶食が推奨されていたのはおそらく20年前くらいまでです。なるべく早期から食べさせたほうが回復が速くなることがわかっています。
犬の膵炎には低脂肪食が推奨されますが、個人的には、給餌が難しい場合にはあまり低脂肪にこだわらずに与えております。
膵炎が治った後は、「無治療」「低脂肪食を食べさせ続ける」のどちらかを選択することになります。再発するようであれば低脂肪食を続けるのがよいでしょうけれども、初発の場合はどちらでもよいかなと個人的には思っております。低脂肪食を使う場合は他の疾患との兼ね合いも考える必要があります(特に腎臓病)。
慢性腎臓病の犬は膵炎を発症するリスクが高いと言われています。食事に関しては、腎臓病用フードは高脂肪であるため膵炎には適していないのですが、仕方なく使う場合もあります。どちらの病気の治療を優先させるかはケースバイケースです。
心臓病の犬も膵炎を発症するリスクが高いと言われています。心臓病の犬が膵炎を発症した場合は、輸液に関して頭を悩ませることになります。大量に輸液を行うと肺水腫になってしまうため様子を見ながら少なめに行いますが、治療効果も不十分となる可能性があります。
あとは余計な話ですが、心臓病の犬の体調が悪化した場合に膵炎を見逃されて肺水腫と誤診される事例もあるようです。腹痛で呼吸が速くなっているとたしかに紛らわしいとは言えます。膵炎と肺水腫の治療は真逆(輸液と利尿剤)ですから、膵炎に対して肺水腫の治療をするとむしろ悪化させてしまいます。先日そのような転院事例がありましたが、治療を変更したら治りました。ブレンダZが効いたのかもしれません。
・犬の急性膵炎は、症状と検査結果から総合的に診断する
・膵炎以外の病気がないかどうかの確認も重要であり、安易な診断は危険
・絶食はさせない、むしろ強制的にでも食べさせたほうがよい
・標準治療は輸液、鎮痛、制吐、低脂肪食給餌(場合によりステロイド、ブレンダZも使用)
・ブレンダZに関してはエビデンスの蓄積が期待される